世界一早い「ゲド戦記」インタビュー(完全版)
前口上
依田謙一
昨年末、ヨミウリ・オンラインの「ジブリをいっぱい」で、鈴木敏夫プロデューサーのインタビューを掲載しました。今年7月公開のスタジオジブリの新作「ゲド戦記」(宮崎吾朗監督)について、スタジオ近くの「秘密の部屋」でじっくり語っていただいたものです。
ご本人からは事前に「インターネットはスペースの心配をしなくていい媒体だから、語ったそのまま掲載してほしい」と言われていました。こちらもその考えに賛同し、映画化に至った経緯を詳しく伝えるため、できる限り省略せず、記事にしたつもりです。
しかし、掲載された記事に対し、鈴木プロデューサーから「これではダイジェストじゃないか」と電話がありました。
誤解を覚悟で言えば、世に存在するインタビューは、そのほとんどが「編集」されています。そもそも、人は物事を常に論理的に考えているわけではありませんし、会話というのはしばしば脇道に逸れるものです。質問も、前後の脈絡なく行われる場合があります。
こうして散らばった言葉は、テレビ、雑誌、新聞の媒体を問わず、“受け手のために”整理されます。今回のインタビューも、同じ目的で編集しました。一方、この作業には、送り手の思い込みが入りやすいという危険もあります。
今度は誤解なきよう説明すると、鈴木プロデューサーは普段、喋った内容についてああしてほしいこうしてほしいと言うことをほとんどしません。このあたりは、鈴木さんが尊敬し、同じような考えを持っていた堀田善衞さんの影響かも知れません(こうやって話は脇道に逸れます)。
その鈴木プロデューサーが電話口で、「いいですか、今回はとても慎重なんですよ」と言っていました。それは、駿監督と吾朗監督の親子関係を心配してのことのようでした。それを象徴するように、インタビュー中、言葉を選ぶため、しばしば考え込んでいたのを覚えています。
それから数週間後、「ゲド戦記」の制作を担当するジブリの石井朋彦さんから「インタビューの完全版を掲載したい」という依頼がありました。
私がジブリを訪ねると、鈴木プロデューサーはこう言いました。
「その作業は依田さん(=私)にやってもらったら? ペナルティーがあるんだから」
ペナルティーかどうかともかく、この誘惑は魅力的でした。実は私自身、日頃から「編集されないインタビュー」を読みたいと思っていた一人なのです。
インタビュー原稿ができ上がる過程で、喋った内容がすべて書き起こされている「ベタ起こし」というテキストが存在しますが、私は常々、実はこれが一番面白いんじゃないかと思っていました。
もちろん、このテキストは、原稿と呼ぶには未整理な部分もあります。話の順序もよく変わります。しかし、受け手がこうしたありのままの言葉を目にすることは滅多にありません。私はこの「実験」には意義があると思い、提案に乗ることにしました。それに、そもそも意義のないペナルティーは単なるいじめですから(また話が逸れました)。
それでは、長くなりましたが(そしてこの後も長いですが)お読み下さい。
何故、「ゲド戦記」だったのか
 ――こんな所に隠れ家があるんですね。
――こんな所に隠れ家があるんですね。
鈴木 あれ、来るの初めてでしたっけ? まぁスタジオだとおおっぴらにできない話もありますからね、こういう場所があると助かるんです。
――しかも鈴木さんの後ろには、ドラえもんの座椅子が……。
鈴木 好きなんですよ、ドラえもん。
――なかなか見られない絵ですよ。せっかくなので写真を撮ってもいいですか。
鈴木 いいけど、何に使うのよ。
――後で考えます。
鈴木 仕方ないなぁ(笑)。
――「ゲド戦記」のインタビューは、今回が初めてですか。
鈴木 正確に言うと、この前、朝(日新聞)、毎(日新聞)、読(売新聞)、共同通信、それからスポーツ報知の記者を呼んで懇親会という形では語りました。なぜ今、「ゲド戦記」だったのか。監督はなぜ、吾朗君だったのか。そして親父(宮崎駿)はそれをどう思っているのか。
――今日お聞きしたいのはまさにその3つです(笑)。
鈴木 実は今から20年以上前に一度、宮(崎駿)さんと「ゲド戦記」の映像化を企画したことがあったんです。「風の谷のナウシカ」(1984年)を作る前。
――そうなんですか。
鈴木 確か67年だったと思いますが、原作がアメリカで発表されて、数年後、日本で翻訳版が出たら、宮さんがはまりましてね。その影響で僕も読んだら、本当に面白かった。やがて「ナルニア国物語」「指輪物語」と合わせて3大ファンタジーと呼ばれるようになるでしょう。あの時いろんな人が3作品の映像化を実現しようとしていて、今思えば宮さんもその一人だったんですが、うまくいきませんでした。もしあの時、「ゲド戦記」をやっていたら、「ナウシカ」はなかったかも知れません。
 ――特にどの点に惹かれたのですか。
――特にどの点に惹かれたのですか。
鈴木 力や魔法を手に入れて敵と戦うそれまでの冒険活劇やファンタジーと違い、戦う相手が「自分」であるということが衝撃的でしたね。これはル・グウィンさんの発明ですよ。だって、「ゲド戦記」がなければ、「スターウォーズ」シリーズもなかったわけでしょう。
宮崎駿監督は、どう思っているのか。
鈴木 その後、何度も繰り返し読んでいたんですが、数年前に読み返したら、特に第3巻が面白くてね。今の時代にぴったりだと思ったんです。それでええと……。ちょっと整理しますね(しばらく考え込む)。とにかくそんな経緯で、ずっと映像化したいと思っていたんです。そうしたら3年ほど前、日本語版を翻訳した清水真砂子さんを通じて、ル・グウィンさんがその後、宮崎作品をご覧になり、彼に映画化してほしいと言っているという話が舞い込んできた。僕としては渡りに船でしたが、宮さんは悩んでしまった。
――なぜですか。
鈴木 何しろ「ハウルの動く城」(2004年)の制作で頭がいっぱいだったし、自分が作りたいと思っていた頃からずいぶん時間が経って、「今の自分にできるだろうか」という思いもあったようです。まぁ監督が吾朗君に決まるまでいろいろあるわけですが、それはとりあえず置いといてお話すると、ル・グウィンさんのもとに映像化の許諾をもらいに行くことになるのは、実は宮さんなんです。僕も一緒に行きましたけど。最初は、吾朗君が行くはずでしたが、それを聞いた宮さんが「おかしい」と言い出したんですよ。監督は時間があるなら一枚でも多く絵を描くべきで、原作者へ許諾をもらいに行くのはプロデューサーの仕事だろうと。そこでふと思いついて、「じゃあ宮さんと僕で行きましょう」と提案しました。宮さんは「えぇっ?」と動揺していましたけど、「ファンなんだからいいでしょう」と説き伏せました(笑)。
――会った際の様子はどうでした?
鈴木 今年(05年)6月、「ハウル」の全米公開前に行ったんですが、ル・グウィンさんには宮さんが行くことを隠しておいたんです。それで、宮さんを「彼が宮崎吾朗です」と紹介したら、「ずいぶんお歳をめした方だったんですね」って(笑)。本人は部屋に入ってきた時から分かっていたと思いますが、そのことには一切触れずにいてくださったおかげで、和むことができました。
――交渉は順調でしたか。
鈴木 いろいろありましたよ。何しろ彼女は宮崎「駿」に映画化してほしいと言っていたわけですから。まず宮さんが「今日は俺に話をさせてくれ」と、「ゲド戦記」への思いを話し始めました。「本はいつも枕元に置いてある。片時も放したことがない。悩んだ時、困った時、何度読み返したことか。告白するが、自分の作ってきた作品は『ナウシカ』から『ハウル』に至るまですべて『ゲド戦記』の影響を受けている」と。そして「作品を細部まで理解しているし、映画化するなら世界に自分をおいて他に誰もいないだろう」と言い切った。しかしその直後、彼はこう付け加えました。「この話が20年以上前にあったなら、自分はすぐにでも飛びついていたと思う。だが、自分はもう歳だ。そんな時、息子とそのスタッフがやりたいと言い出した。彼らが新しい魅力を引き出してくれるなら、それもいいかも知れない」。そしてこう締めくくった。「息子がやるであろうスクリプトには自分が全責任を持つ。読んで駄目だったら、すぐにやめさせる」と。
――ル・グウィンさんは?
鈴木 冷静でしたね。このあたりが日本人と米国人の違いというか、情に負けず、非常に理性的なんです。彼女は「二つ質問があります」と言いました。一つ目は「映画化されるのは第3巻が中心だと聞いていますが、登場するのはすでに年老いて中年になったゲドです。今のあなたにこそふさわしいのではありませんか」。二つ目は「あなたは吾朗さんが作るであろうスクリプトに対して全責任を持つと言いましたが、それはどういう意味ですか」。あ、三つ目もありました。「駄目だったらやめさせるとはどういうことですか。今日、あなたは映像化の許諾を取りに来たのではないのですか」。それを聞いた宮さんは僕の方を向き、「俺、何かまずいこと言ったかな」って(笑)。
――何と答えたのですか。
鈴木 僕は「全責任を持つというのは、つまりこの映画のプロデューサーをやるんですかって聞いているんです」と答えました。そうしたら宮さんはル・グウィンさんの前で突然、大きな声を出して、「冗談じゃない! 親子で一本の映画に名前を並べるなんてみっともないことはできない」って。率直な人なんです。
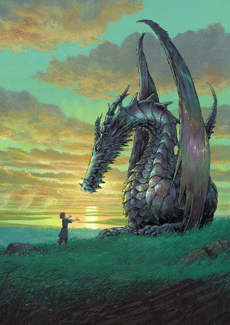 ――話が紛糾してしまった。
――話が紛糾してしまった。
鈴木 アメリカ人には意味不明ですよ(笑)。どうなるかと思っていたら、彼女の息子のテオさんが「今夜は一緒に食事もしますし、大事な話は後でしませんか」とその場を取り直してくれました。実はテオさんは、交渉前に日本に来てくださり、僕や吾朗君といろんな話をしていたこともあって、味方になってくれたんです。これは僕の勝手な推測ですけど、偉大な親を持った者同士で相通じるところがあったのかも知れません。まぁそんなことがあって、ル・グウィンさんから「では景色でも見ていて下さい」と言われたんですが、今度は事前に送っておいた2枚の絵についての話になった。一つはポスターになっている吾朗君が描いた竜とアレンが向き合った絵。もう一つは宮さんが描いた第3巻のホートタウンの町の設定の絵なんですが、宮さんが突然、吾朗君の描いた絵を指して、「これは間違っていますよね」と言い出したんです。それで今度は自分の絵を指して、「これが正しいと思います」って。
――何しに行ったのか分からないじゃないですか(笑)。
鈴木 あんまり面白おかしく聞こえたら問題ですが、事実ですよ。そこから、なぜ間違っているかという説明が始まった。「このポスターのように、竜とアレンが目を合わせているのはおかしいじゃないですか。そうでしょう、ル・グウィンさん」と。
――決裂の危機ですね。
鈴木 何とかその場は別れましたけどね。それで夜の食事のとき、最初は関係ない話に終始していたんですが、途中で、テオさんがル・グウィンさんに「大切なお話があるんじゃないの」と促したんです。彼女はしばし沈黙した後、彼女の前に座っていた宮さんの手をとって「吾朗さんにすべてを預けます」と言いました。それを聞いた宮さんは、「うぅ…」と泣いていました。彼は激情家ですからね。冗談っぽく聞こえるかも知れませんが、本当の話です。それで、そろそろなぜ、吾朗君を監督に抜擢したかという話ですが……。
――お願いします。
何故、宮崎吾朗を監督に抜擢したのか。
鈴木 前提として、ジブリの今後という問題があります。高畑勲は70歳。宮崎駿も65歳。2人合わせて135歳。これに僕の歳を足せば200歳に近づいている(笑)。まぁそれはともかく、このままいけばジブリは終わりますよ。でも、もともと2人の映画が作りたくて始めた会社ですし、僕もある満足は得ている。心のどこかで「もうスタジオを閉じてもいいかな」と思っているところもありますが、やっぱりこれからを考えている若い人に対する責任もあります。だけど、宮さんは作る方は天才でも、教えるのは決してうまくない。先生としてはむしろ下手です。彼を助手席に乗せて運転すればすぐに分かりますよ。特にマニュアル時代は大変でした。「はいセカンド、はいサード、はいトップに入れて!」と横からいちいち口を出すから、大抵の人は運転がうまくできない。挙句の果てはノイローゼになってしまうんです。
――それは大変ですね(笑)。
鈴木 「魔女の宅急便」(89年)も「ハウル」も、最初は別の人が監督をやる予定だったのが、結局宮さんがやることになったように、映画作りでもそういう光景を何度か見てきました。もちろん宮さんに悪気はないんですよ。ただ、彼は一生懸命教えているつもりでも、受け取る側は、あまりに豊富な知識と経験を押し付けられるので、大変なんです。十二指腸潰瘍になって来なくなってしまう人もいたくらい(笑)。その点、「猫の恩返し」の森田(宏幸)君の場合は、いい意味で鈍感なのが良かった。何を言われても、「それは違うんじゃないですか」と平気で返せたからできた。黒澤(明)さんもそういうタイプだったみたいですからね。「椿三十郎」(62年)だって堀川弘通さんがやるはずだったのが黒澤さんになってしまったようにね。それと、ジブリでは若い人が一度作ってもその後が難しいんです。
――というと?
鈴木 うまく言いにくいんですが、「猫の恩返し」を例に取ると、試写が終わった直後、宮さんがすごく怒った顔で僕の部屋に入って来たんです。僕の部屋というのはいつもドアを開けっ放しにしていますが、その時は珍しくドアを閉じて、「あいつにどうして今時の若い娘の気分が分かるんだ」と腹を立てていました。褒めているんですよね。実は「ハウル」はその反動でもあって、ソフィーというのは、宮さんなりのハル(=「猫の恩返し」の主人公)なんですよ。今の話と関係あるかどうか……でも、なかなか若い人に作るチャンスが巡って来ないのは確かです。宮さんも歳ですからね、時々極端なことも言うわけです。「俺はもう若い力は信じない。年寄りだけで作っていく!」とか。まぁそれもいいんですけど、僕としてはそういうわけにもいかないから、いろいろ考えるわけです。それで吾朗君を間に挟めばうまくいくんじゃないかと。
――でも、アニメーションの制作経験はないわけですよね。
鈴木 それは気になりませんでしたよ。彼がジブリ美術館を宮さんのイメージ図をもとに作った時だって、造園の経験はあっても建築はやったことなかったんですから。
――ジブリ美術館の時は、なぜ吾朗さんに白羽の矢を立てたのですか。
鈴木 中学生の頃から彼を知っていましたが、おじいさんの葬儀で久々に会った際、「吾朗です」と声を掛けられたのが妙に印象的だったんです。僕の目をしっかりと見て、視線を放さなかった。美術館の話が持ち上がった際、ふと顔が浮かんだんです。それで宮さんに吾朗君にやってもらうのはどうかと話したら、「鈴木さんが説得して、本人がやるというなら仕方ない」ということになって。
――吾朗さんの答えは。
鈴木 二つ返事で了承してくれました。それでいざ仕事してもらったら、ありがたいと思ったことが二つあった。一つは、ジブリ美術館を完成させた上で、運営まで見事にやってのけてくれたこと。もう一つは、宮さんの描くイメージで曖昧な部分があると、断固として受け付けなかった。これは非常に頼もしく思えた。宮さんは美術館を作る際も、ありとあらゆることに口を出しましたが、頭の中にあるものは空想の産物の場合もある。それに対して、吾朗君は「駄目なものは駄目」と明快だった。そういう自分の考えを実行に移す彼のパワーを見ているうちに、もしかしたら映画の仕事もできるんじゃないかと思ったんです。それで「ゲド戦記」の話があった際、「ジブリ美術館のこれからを考えるなら、ジブリのこれからに無関心ではいられないだろう。企画に参加してみないか」と聞いたら、すぐに「美術館と関係があるので」と答えた。それで去年の秋(03年10月)、企画を立ち上げるため、あるアニメーターと僕、それに吾朗君と石井(朋彦)という若い制作スタッフでこの部屋に集まりました。
――その時点ではまだ「監督」ではなかったんですね。
鈴木 そうです。それで話を進めていくうち、僕としては監督をやってもらいたいと思い始めていましたが、そのためにはいろんな人に話をしなきゃならない。そこで、ある程度企画が見えたところで、宮さんに「本格的に準備するにあたり、吾朗君にアドバイザーとして関わってもらいたい」と話したんですが、大反対でしたね。「吾朗は関係ないだろう」って。スタジオの皆に話した際も、彼が参加することに様々な意見がありました。そのうちに誰が絵を描くのかということになったので、右往左往しながら、まずは絵コンテを描いてもらうことにしたんです。
――どう描き始めたのですか。
鈴木 最初に注文したのは、見よう見まねでやりなさいということ。親父が描いた絵コンテをそばに置いて、自分がほしいカットがあったら、それを参考にしろと。そして、その作業は人前で堂々とやりなさいと言いました。また、彼自身もいろいろ考えて、ジブリ美術館でやった「ピクサー展」で得た知識をもとに、カードに絵を描き、それを縮小コピーして張り付けるという方法を編み出した。やがて内容が固まってきたところで、ル・グウィンさんの元へ許諾をもらいに行くことになったので、僕から「竜とアレンが向き合っている絵を描いてくれ」と依頼しました。それから「横から見たんじゃなく縦から見た構図にしてくれ」と付け加えました。なぜか。親父が描かないアングルだからです。この絵ができた時、僕は吾朗君が監督としていけると確信しました。それで、宮さんにちゃんと話さなければと会いに行ったら「鈴木さんはどうかしている」と怒り出した。「あいつに監督ができるわけがないだろう。絵だって描けるはずがないし、もっと言えば、何も分かっていないやつなんだ」と。そこで僕が吾朗君の描いた絵を見せたら黙ってしまった。一枚の絵ってそういう力があるんですね。そこで、僕からはっきり言いました。「進めますよ」。本人はしばらく呆然としたままでしたけどね。
――吾朗さんが描けるということは以前から知っていたのですか。
鈴木 僕はね、きちんと観察さえできれば絵は誰でも描けると思っています。これは「月刊アニメージュ」という雑誌をやっていた時のことですが、普段絵を描かない編集部員に、編集後記用の自画像を描いてもらったことがあったんです。皆、最初は無理だと言っていましたが、自分の顔を丁寧に観察し始めたら、ちゃんと最後まで描けた。しかも、一生懸命描いた迫力があった。吾朗君も、打ち合わせの最中に似顔絵を描いていたので、観察ができる彼ならできると思っていました。実際、彼は描けましたし、この2年間に長足の進歩を遂げました。
――完成した絵コンテを見た感想は。
鈴木 これは僕よりも他の言葉で紹介した方がいいと思います。名アニメーターの大塚康生さんは(とシワシワ声でモノマネを始まる)、「いひゃぁー鈴木さんびっくりしましたよぉ。すごいですねぇ。映画として素晴らしいし、つなぎ方も完璧でしたぁ」と絶賛した上で、「ところで誰が描いたんですか」と聞いてくるので、「吾朗君ですよ」と答えたら、「いや、そうじゃなくて、吾朗君が指示して描いたのは誰ですか」とさらに聞くので、「いゃ、だから吾朗君です」と答えたら、「ふぇっ! 蛙の子は蛙だったんだ。びっくりしたなぁ。小さい頃から知ってるけど、へぇ」と心底、驚いていました。また、庵野(秀明)に見せたら、「これは完全に宮崎アニメですね」と舌を巻き、「吾朗君はいくつですか」と聞いてくるので、「38歳だよ」と答えたら、「どうしてもっと早くやらせなかったんだ」と言っていました。
――駿監督は絵コンテを見たのですか。
鈴木 見ていません。今も混沌とした状態で、二人はまったく口をきいていません。つい最近まで宮さんが美術館用の短編を同じフロアで作っていたのですが、お互いの声が聞こえても決して接点を持とうとしなかった。部屋の中ですれ違いそうになるとすっとお互いを避けて踵を返していたほどですから。
――吾朗さんはアニメーションへの関心がずっとあったのですか。
鈴木 僕には分かりません。普通は自分の親父の近くで仕事をするのは嫌なはずですが、どこかで父親の仕事への関心というものはあったのかも知れません。理由は分かりませんが、彼がジブリ美術館の仕事を引き受けた時、それを感じました。今、彼は自らジブリのホームページで日々の思いを綴っていますから、そこで明かされていくかも知れません。
――吾朗さんの演出の特徴は。
鈴木 彼はアニメーターの絵を見て違うなと思う部分があると、実際に自分で演技して見せるんです。実に明快な方法で、アニメーターはそれを見て描けばいい。これだけイメージがはっきりしている監督はなかなかいません。
――駿監督もそういう演出をされますよね。
鈴木 確かに。そういう意味では似ているかも知れません。
――ところで、宣伝戦略はどうするつもりですか。
鈴木 新人監督ですから、しっかりやりますよ。「ハウル」のような「宣伝をしない、宣伝」ができるのは宮崎駿だからです。それに彼の名前を宣伝に使おうとは思っていません。
――駿監督のクレジットはどうするつもりですか。
鈴木 悩んでいます。苦し紛れに珍案奇案も考えました。「父 宮崎駿」とか(笑)。だって「アドバイザー」とかもっともらしいこと言っても仕方ないでしょう。あえてもう一つ候補があるとすれば「ゴッドファーザー 宮崎駿」。
「ゲド戦記」で描きたいこと。
 ――最後に、鈴木さんが今、この時代に「ゲド戦記」を送り出そうと思ったきっかけを教えて下さい。
――最後に、鈴木さんが今、この時代に「ゲド戦記」を送り出そうと思ったきっかけを教えて下さい。
鈴木 一言で言えば、希薄になってしまった「現実感」を描けるような気がしたからです。
――「現実感」?
鈴木 日本人全体が陥っているかも知れないことですが、当事者意識の欠如ということです。この前の選挙で、郵政民営化を賛成か反対かを一人一人の国民に問いましたが、果たしてそんな必要があったのか。それは、会社がつぶれそうかという時に、社員に「どうしましょうか」と聞くことでしょう。同じように、憲法改正や増税についても賛成が増えている状況も疑問です。僕はそれを見て、皆、庶民でなくなってきているなと感じます。この国を何とかするためにそれをやるという発想は、庶民じゃなくて為政者でしょう。国がやることにたて突くのが庶民じゃなかったんですか。増税して改憲して、それが何につながるか。「欲しがりません勝つまでは」ですよ。だから皆に目を覚まして欲しいし、小泉内閣の虚像をはがして欲しい。増税になって一番困るのは誰か分からない状態が、僕の考える当事者意識の欠如ということです。吾朗君は「人としてまっとうに生きること」をテーマにしていますが、それも当事者意識ということとつながってくる。まぁこれは作品を通して彼が表現していくことなので、このくらいにしておきますが。
――そう言わずに、もう一声お願いします。
鈴木 皆がそんなに立派にならなきゃいけないんでしょうかということです。別の例で言えば、携帯電話がどんどん高機能になっているでしょう。僕は見ていて怖い。SuicaもEdyも使ってみましたが、携帯電話がお財布になったり、メールができたり、電車に乗れたりということは、確かに便利かも知れない。でも、人間って基本的にだらしないでしょう。それが、何もかも一つになって、なくすことができないものを持てということは、少なくとも僕は受け入れたくない。要するにだらしないことをするなと求められているんですよ。そういう便利さという名の「立派」のために切り捨てられていくものがあるんじゃないですか。関係ない話かも知れませんが、今、商法の改正で四半期ごとに決算を報告しなきゃいけないんです。なぜかといえば、二度と大量の不良債権を生まないという目的があるから。日本の経営者たちは決算書もまともに読めないからあんなことになったんだと。しかし、そういうことをきちんとしている人に面白い経営ができますか。計算ができないから無茶をするのであって、無茶をするから面白いんです。
――ええ。
鈴木 宮さんだってそうですよ。話は逸れましたが、魔法が使えるはずだった世界で、魔法が使えなくなり、大きな町へ行けば、人々は右往左往しているばかり。流行っているものといえば、人身売買と麻薬。そういう状況で少年と魔法使いが出会う。さぁどうなるか――。ハイ、もう十分喋ったよね(笑)。



