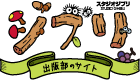ページ内容
週一回更新コラム「ゲド戦記の作り方」
2006年2月24日
全ての道はローマに通ず ─世界観(2)─
明日(2月25日(土))から、全国の劇場で、映画「ゲド戦記」の予告編が上映されます。昨日、日本テレビ系列の番組でも、同・予告編が放映されました。
初めて明らかになった登場人物や、ストーリーの片鱗は勿論、ジブリ背景美術部が腕をふるった、映画の背景=世界観に注目される方も多いことでしょう。映画は、キャラクターや物語だけではなく、スクリーンの向こうに広がる、世界観そのものを楽しむことが、大きな醍醐味です。
前回は、「全ては一枚の絵から始まった」と題して、映画「ゲド戦記」が、吾朗監督の描いた一枚の絵から動き出した瞬間のことを書きました。今回は、世界観の第二回目。映画の世界を作り込むために、監督とスタッフが挑んだ、ある試みについて、書きたいと思います。
映画を作るときはまず、世界を描かなければならない。
これは、高畑勲監督の言葉ですが、企画準備時に、吾朗監督以下、メインスタッフは、鈴木プロデューサーに何度もこう言われました。曰く、この世に存在しない架空の世界を作る時、映像=世界観が説得力のあるものではなければ、お客さんは映画に入ってゆく事が出来ない。いくら美味しいストーリーや、目に華やかなキャラクターを調理しても、それを盛る器=世界が無ければ、お客さんのもとに、映画を届ける事は出来ないからです。
あれは、2005年の4月中旬の事だったと思います。吾朗監督が「映画を象徴する一枚の絵」を描き、映画が動き出してから、メインスタッフが、世界観を更に作り込むための作業を続けていたある日のこと。宮崎駿監督がひとつのアドバイスをくれたのです。
先の、鈴木プロデューサーのインタビューにもある様に、宮崎駿監督は「ゲド戦記」の制作に反対をされていますが、後にも(おそらく)先にも、この一度だけ、鈴木プロデューサーと僕を通して、大きなサジェスチョンを下さったのでした。
「(物語の舞台の)モデルは、ヨーロッパの絵画の中に、沢山ある。まず、絵を知らなければならない。ヨーロッパの絵画を集めなさい」
以降の話をまとめると、次のようなものでした。
1.無から有を生み出そうとしてはいけない。古今東西の絵の中に、映画のモデルとなる世界は、必ず存在する。その絵を見つけること。
2.映画の時代背景と、探すべき絵画との時代背景・モティーフに注目すること。
3.その世界を、ひと言で表す言葉を探すこと。
映画の世界観を表現するのに最も適した時代──それを描いた絵を、歴史的背景も踏まえて探し出し、参考にすることが、作品世界に実在感を持たせる、最も大事な事だ、と。
映画「ゲド戦記」は、原作の第3巻『さいはての島へ』をもとに作られています。世界の均衡が崩れ始めた多島海世界・アースシーの各地で起こった災いの謎を解くために旅立つ、王子アレンと大賢人ゲド。映画も、まさに世界のバランスが崩れ始めたところから、始まります。
あらゆる文明は、発展し、絶頂を極めた後に、衰退へと向かう。それが理です。現代文明もその例外ではないように、栄えたものはいつか、終わりを迎えます。
『ゲド戦記』の魔法世界もまた、緩やかにその力を失い始めている。それが、原作『さいはての島へ』の世界観の骨子でした。アースシー世界の興亡を踏まえずして、『ゲド戦記』の映画化はあり得なかったのです。
そんな、ある種、黄昏を迎えつつある世界を表現した絵画は何か。
吾朗監督とスタッフの、絵画探しが始まりました。
はじめに、ゴロウ監督が挙げたのが、ピーテル・ブリューゲル Pieter Brueghel the Elder(1525-1569)でした。ブリューゲルは、「雪中の狩人」や「バベルの塔」等で有名なベルギー・フランドルの画家です。僕も一昨年、ウィーン美術史美術館で実物を見てきましたが、所謂美術書で代表作として紹介されるこれらの作品よりも、吾朗監督が注目したのは、ボッシュ Hieronymus Bosch(1450-1516)の、ペシミスティックな空想世界に影響を受けた「反逆天使の転落」や「謝肉祭と四旬節の喧嘩」等でした。
人々は
せわしなく動き回っているが
目的は無く、
その目に映っているものは、
夢か、死か、
どこか別の世界だった。
予告編に記されたボディコピーを、まさに絵画に起こした世界が、そこにありました。実際に、物語の舞台となる街に登場する人々は、これらの絵から生まれたであろう事を、僕はラッシュ上映を観て、確信しています。
その後、様々な試行錯誤を経て、最終的に行き着いたのが、宮崎駿監督のアドバイスによって知ることになる、クロード・ロラン Claude Lorrain(1600-1682)の絵でした。
クロード・ロランは、17世紀の、フランス出身の古典主義風景画家です。幼くしてローマに行き、菓子職人の見習いになりますが、やがて絵画の道に進み、ローマを拠点に、多くの絵を遺しています。
素人の僕が、大雑把な解説をしてしまうと、ロランの絵には、ひとつの特徴があります。ロラン絵画の多くは、そのモティーフとして、ローマの神殿が描かれています。深緑の波が打ち寄せる港には、白亜の神殿が建ち並び、古代の装束を着た人々がひしめいている。暮れなずむ夕陽を背に、今まさに接岸しようとしている船。まるでロランがその場に立ち会い、活写したかのようです。
しかし、ロランが生きた17世紀当時、ローマの神殿はその多くが廃墟でした。ロランは、その廃墟の中に、自らが思い描いた、古代の理想風景を描き出したのです。
「今は廃墟だが、かつてここは、こうだったに違いない」──と。
次に参考にしたのは、18世紀末から19世紀にかけて、ヨーロッパで興ったロマン主義の画家たちによる、廃墟趣味の絵画でした。ドイツのカスパール・ダヴィッド・フリードリヒ Caspar David Freidrich(1774-1840)や、アーノルト・ベックリン Arnold B¨ocklin(1827-1901)等、古代ギリシャやローマの遺跡をモティーフに描かれた廃墟絵画の中には、黄昏の世界を描く、多くのヒントが隠されていました。
当時、宮崎駿監督が、こう言っていた事を思い出します。
人類の生み出した建築は、ローマ時代に最も凄いところまで行き着いてしまった。その後に、ローマを越える建築は現在に至るまで生まれていない。これからも、ローマ以上のものが生まれることはないだろう。人類の黄昏に向かってゆく我々には、そういう気分が良く解る。人によっては、それは退廃だと言うかもしれないけれど──。
絶頂を極めた建築物が、やがて廃墟となり、そこに、黄昏の時代を迎えた人たちが住んでいる──。
これらが、吾朗監督とスタッフの中で符合したとき、映画「ゲド戦記」をひと言で表す言葉、「壮麗なかつての都に、人々が白アリの様に巣くっている世界」が生まれたのです。
吾朗監督は、その世界をまるで旅してきたかのように、画用紙にイメージを描き続けました。
架空の世界を舞台にした映画に、どこか違和感を抱き、上手く入っていけない経験が、皆さんもあると思います。確かに見たことはないけれど、本当にありそうに思えない。そうした映画は、往々にして、世界観に実在感が無い場合が多い。
作るという行為は、思い出すという行為に似ていると言います。何か新しいものを観たときに、一方でどこか懐かしいと感じる事がある。人間のDNAの中に眠っている太古の記憶を呼びさます為には、先人の描いた知恵を、思う存分借りた方が良い。しかし、ただ無作為に変わった世界を持ってきても、世界はちぐはぐになってしまうだけです。そこには、映画の中で描くべき時代背景や、人々の抱いている気分が、流れていなければならない。その為には、探すべき絵画や建築資料の、歴史的・時代的背景を踏まえなければならないのだという事を、この準備作業は教えてくれました。
他にも、当時、東京・上野の国立西洋美術館で開催されていたジョルジュ・ド・ラ・トゥール Georges de La Tour(1593-1652)展を見にいって得た着想や、吾朗監督が興味を持って調べていた、ビザンチン世界の建築物や壁画迄、様々な世界をモティーフに、映画「ゲド戦記」の世界は作り上げられています。
映画監督は、自らのイメージを具体的にスタッフに伝える力が必要とされますが、吾朗監督はヨーロッパ文化に造詣が深く、かつて造園や建築を手がけた経験もあり、その知識と経験は、企画段階から現在に至るまで、現場で遺憾なく発揮されています。
次回は、「映画の主人公は2種類しかない」と題して、キャラクター作りについて、書きたいと思います。