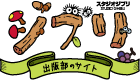ページ内容
週一回更新コラム「ゲド戦記の作り方」
2006年1月 2日
原作と、どう向き合うか ─企画とは何か(4)─
明けましておめでとうございます。
昨日、東京は薄曇りの元旦でした。
2006年、第一回目の更新は、毎週月曜日に更新している「ゲド戦記の作り方」です。
これまで「企画とは何か」と題して、映画の企画について書いてきました。今回は、その最終回。原作といかに向き合うかというお話です。
原作と、どう向き合うか ─企画とは何か(4)─
皆さん、原作モノの映画を観たとき──それが特に、自分の好きな原作だったとき、
「原作と違う!」
と思った事はありますか?
逆に、登場人物も、ストーリーも、原作そのままに作られているのに、
「なんだかつまらないナ」
と感じた事もあるのではないでしょうか。
これは、とても難しい問題です。ストーリーや登場人物に変更を加えることで、原作を愛読する人々のイメージを壊してしまう事がある。かといって、原作をそっくりそのまま忠実に再現しても、内容的に成功しない場合もある。あまりに難しすぎて、一概には言えません。
映画は、ある特定の時期に、ある時代を生きる人々へ向けて作るものですから、その時代に合わせた、切り口と解釈をもって作らなければなりません。上映時間の制約や、文章を映像化することによって生ずる、制限や飛躍。文章と映像の垣根を越えるために必要となる様々な要因によって、原作に完全に忠実という映画はあり得ません。
それでも、原作を扱う場合に、必ず守るべきことがある。それは、原作者が物語を通して何を伝えたかったのか──その核心の部分を読み取る努力をする、という事です。それが、原作を扱うときの礼儀作法である。僕らは「ゲド戦記」の企画を始めた頃、鈴木プロデューサーに、何度も言われました。
そもそも原作者は、何をやりたかったのか。何故に、それを書いたのか。必ず作品を通して、訴えたかったことがある筈だ。それを見つけてからでなければ、ストーリーを考えたり、キャラクターを作ったりしてはいけない。(鈴木語録より)
「ゲド戦記」の企画が動き始めてから、監督以下、僕らが最も時間をかけたのは、原作を読み込み、分析する事でした。重要な台詞や描写を抜き出し、登場人物を分類し、ストーリーの構成を表にまとめ、作品が書かれた時代の歴史的背景を勉強しながら、原作者が作品を通して何を訴えたかったのかを話し合う。行き詰まったら、何度でも原作に立ち返る。その繰り返し。
「ゲド戦記」の企画を立ち上げてから、誰よりも原作を読み込み、深い洞察と理解を示したのが、宮崎吾朗監督でした。彼と原作について議論をする度に、こちらが思いもよらなかった視点が目の前に立ち現れて、舌を巻いたものです。今でも、彼の作画机には原作が並んでいて、何かに行き当たると、必ず原作に立ち返っている横顔を目にします。
それでは今、僕らが作っている「ゲド戦記」はどういう映画なのか。
今、ここで書くべきではないでしょう。監督が作品に込めた想いは、「監督日誌」で追々明らかになってゆくことでしょうし、この夏、皆さんに劇場で確かめて頂きたい、と願っています。
そこで今回は、ひとつ具体的な作品を、例をあげてみたいと思います。
少し前の映画になりますが、2003年に公開されたドイツ映画「飛ぶ教室」は、児童文学の名作を現代に向けて映画化した、優れた映画でした。
原作は、ドイツの国民的作家、エーリッヒ・ケストナーが七十年以上も前に書いた、同名の児童文学。高等中学校の寄宿舎で暮らす5人の少年たちが、力を合わせてクリスマス劇を上演するまでの成長劇を、様々なエピソードを散りばめて描いた作品です。
映画では、大きくふたつの点が、原作と変わっていました。
ひとつ目は、舞台を、ベルリンの壁崩壊後の現代ドイツに置き換えたこと。ふたつ目は、少年達ひとりひとりに、現代的な問題や家庭環境が与えられていたことです。
このふたつの設定は、下記の効果をもたらしていたように思います。
ひとつ目は、原作者の描こうとしたテーマが、時代を越えて僕らに伝わってくること。「飛ぶ教室」が出版されたのは1933年。ナチスが政権についた年です。ケストナーの著書の多くがナチスの弾圧によって発禁される中「飛ぶ教室」は出版されました。
映画では、舞台を現代ドイツに置き換えたことで、ベルリンの壁崩壊という、歴史的事実がクローズアップされます。壁が崩壊する前後で、ドイツという国の「自由」がどのように変わったか。それが、映画の大きなテーマでした。反ナチスの立場をとり、「自由」を訴え続けたケストナーの視座が、映画の中にも、しっかりと受け継がれていたのです。
ふたつ目は、子供たちの家庭環境に現代的な問題を組み込む事によって、現代を生きる観客が、より深く感情移入出来る、という点です。子供たちが暮らす寄宿舎の意味合いも当時と大きく変わっている筈ですから、その設定も、現代風に置き換えてありました。
映画「飛ぶ教室」は、原作の生まれたドイツで、大ヒットを記録しました。
日本で公開されたとき、僕も劇場へ観に行きました。時代設定やストーリー、原作を読んだときに抱いたイメージと映画は違っていたけれど、「これはまさしく、『飛ぶ教室』だ」と手を叩いたのを覚えています。
原作を扱った映画が、僕らの心を打つか否かのポイント。それは、原作者の描こうとしたテーマを、映画制作者が如何に深く理解をして映像化するか、という事に尽きるのではないか、と僕は思います。
次回は、映画を通して何を訴えたいのか──テーマについて、書いてみたいと思います。