Main Contents
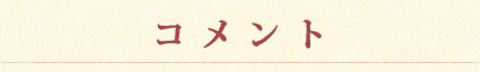
「チベット死者の書」とは 石濱裕美子
精神の探究者であるチベット人がつみあげてきた智慧の書
肉体が機能を停止し最後の息がでたあとの49日間、死者は意識だけの状態(パルド)となり、その後新しい母胎に入って再生する、このような輪廻思想がチベットにはある。そして『チベット死者の書』には、このパルドの期間、死者がパニックを起こさず切り抜けられるように、導くための教えが記されている。
肉体を失った意識はもろもろの外界の刺激から離れることによって穏やかになり、もっとも根源的なものに触れることができる。チベット人にとって死は「仏の意識」(菩提)にもっとも近づくことのできるまれなチャンスであるため、死について積極的に話題にするし、命の期限を宣告されても動じることなく受け入れる。高僧に至っては、死に臨んでは、座禅をくんで瞑想に入り、その中で「死の光明」を迎える。深い瞑想と死は限りなく同じ状態であると考えられている。
『死者の書』によると、肉体が死んだ直後、死者はもっとも微妙な意識の現れである根源的な光と出会う。もし死者の意識がその光の中に入っていくならば仏の境地を得ることができる。しかし、これまでに積み重ねてきた様々な行為の力により、死者の意識はすぐに光の状態から引き戻されてしまう。しばらくすると、死者の意識にはやさしい姿の仏たちが現れる。そして、次の一週間にはその仏たちが今度は恐ろしい忿怒の姿をとって現れ、様々なヴィジョンや音で死者を脅かす。そして最後の一週間、死者の意識はついに母胎を探す再生の旅に入り、次の生へと移行する。
この書の素晴らしいところは、49日にわたって現れる光やヴィジョンはすべて死者自身の意識が作り出したもので一切が幻想であると何度も強調するところである。つまり、『死者の書』とは、精神の探求者であるチベット人がつみあげてきた意識のありようについての智慧の書なのだ。したがって、ここに説かれている光とは、宗教や人種をとわず死に瀕した人が見るという臨死の光や音にも通じる。
現実を別の側面から見直そうとするたびに、思い出されてきた書物
チベットには死者の書が数多くあるが、カルマリンパが発掘したこの『死者の書』が一番注目を浴びているのは、この書がこれまでに何度も世界的な大ブームをひき起こしてきたからである。はじまりはイギリスの神智学者エヴァンス・ベンツがオックス・フォード大学から1928年に出版したこの書の初英訳が、たちまちベストセラーとなり、カール・ユングをはじめとする当代の知識人の愛読書となった。六十年代に入ると、ハーバート大学のティモシー・リアリー博士がLSD体験と『死者の書』に描かれる死者の体験が類似していることを指摘したため、『死者の書』はLSDを吸い反戦を謳うヒッピーたちのバイブルとなった。また、七十年代以後は、生の世界ばかりに目を向け、死の世界を等閑に附してきた現代文明への反省として「メメントモリ」(死を思え)が叫ばれ、『死者の書』は臨死体験の書物として脚光をあびた。
日本においては、1993年にNHKスペシャルでこの『チベット死者の書』が放映されるや臨死体験の一大ブームが始まり、この番組の第一部を書籍化した『チベット死者の書 仏典に秘められた死と再生』(NHK出版)と、第二部の台本を収録した中沢新一氏の『三万年の死の教え』(角川書店)と、チベット語原典からの死者の書の和訳である『原典訳チベット 死者の書』(ちくま学芸文庫)がいずれもベストセラーにランクインし、みながこぞって死について語り始めた。つまり、『チベット死者の書』は我々が今ここにある現実を別の側面から見直そうとするたびに、思い出されてきた書物なのである。
不安にみちた現代人にこそ
チベット人の社会は物質的にはきわめて貧しいレベルにあるが、彼らの心は我々よりずっと平穏である。普段から死を生の一部として意識し、来世に備えて体や言葉や心で善い行いを積むように心がけているため、死を前にしても動じることはない。彼らにとって死は、古くなった着物を脱いで新しい服を着るような感覚であり、怖れるべきものではない。
一方、我々の世界は物質的には豊かであるものの、その心はじつに不安定だ。経済成長が人々に幸せをもたらすという幻想のもと、物欲を肥大させ、競争心や嫉妬心をあおった結果、多くの人は心に不安を抱えるようになった。死の間際まで死をまったく無視して生きるため、死に直面せねばならなくなった時、ひたすら恐怖して一分一秒でも長く生きようとする。生まれてから死ぬまで不安にみちたこの現代人の心を鑑みるとき、今こそ、生のもう一つの半分、死に対する知識を取り戻すべき時がきていることは明かであろう。『死者の書』はその一助となるはずである。
日本で『死者の書』がブームになった1993年の4月、わたしは母をガンで亡くした。たった一人の家族を失った喪失感から、眠れない日々を過ごしていたが、この書を手にし、その根源的な死生観に触れた時、ずいぶんと心が落ち着いたことを記憶している。生は死の一部であり、忌むべきものではないことに気づき、自分の人生を見直す契機ともなった。
親しい方を亡くした方、また近い将来亡くすかも知れない方には、とくにおすすめしたい。
石濱裕美子(いしはま・ゆみこ)
1962年、東京都生まれ。早稲田大学教育・総合科学学術院教授。文学博士。研究対象はチベット仏教世界(チベット・モンゴル・満州)の歴史と文化。著書に『図説チベット歴史紀行』(河出書房新社)『チベット仏教世界の歴史的研究』(東方書店)『チベットを知る50章』(明石書店)など。訳書に『ダライ・ラマ仏教入門』(春秋社)、『ダライ・ラマの密教入門』(光文社)がある。







