Main Contents
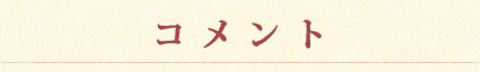
プロデューサー河邑厚徳 「制作の裏側」 その2
「チベット死者の書」の撮影について
典型的な死者儀礼、伝統的な宗教儀礼は、いまや地球上でどんどんなくなっていると思います。「チベット死者の書」を撮影した当時はギリギリですがそれが完璧な形で残っていました。ラダックに入る前は「実際に人が亡くなった時、49日間にわたって法要するというのは本当なのかな?」という思いがありましたし、「もし、それが本当ならばそれは奇跡的なすごい事だな」と感じていました。幸い現地のコーディネーターを介して亡くなった方を探し、取材の許可をもらうことができたので、実際の儀式を映しだしたドキュメンタリーを作ることができました。
冬の撮影になったのは、極寒の地で死者が多い季節だったから、というだけではなく、風景の事もありました。映像効果的に言うと、ヒマラヤの自然が一番よく表現できるのが冬だったんです。それに、以前「シルクロード」も同じ季節に撮影したので、お正月のお祭りがあるなど、その時の記憶が全部使えたということもありました。だから「シルクロード」の取材が、ある意味チベットの下見みたいになりましたね。もちろん、作り手としては同じ事はやりたくないという気持ちがありました。
ドキュメンタリードラマでは、俳優は一切使っていません。現地で、実際にシナリオにある役割の人(お坊さんや小僧さん、家族)を探して演じてもらいました。シナリオはありますが、普段彼らが行っている事をカメラの前で我々の意図を説明してやってもらったので、すごく自然な再現ができました。ドキュメンタリーに一番近い所で作っているフィクションですよね。そこには虚偽がない。唯一あるとしたら、ドキュメンタリードラマの方で亡くなった方を演じている人は、本当は生きている(笑い)ということだけです。
「チベット死者の書」が2部作になった理由
今にして思うとですが、貧しい農家に暮らしているごく普通の老人が、死に対する深い考えをもっていること。そして、泣き女のような存在が生きていて、おじいさんを送るために妻や娘がずっと泣いているシーンなど、本当に事実に圧倒されました。いたれりつくせりで来世に送られるという感じがします。ドキュメンタリーの方で取り上げたスタンジン老人の「あとはただ早く死ぬ事を待ち望んでいる」という姿も、仏様のようです。また、ラストで、彼と赤ちゃんが並んで横になっている画像では「ドキュメンタリーのワンカットにも、ドラマ化した映像に負けない可能性がある」ということを見せることができたのではないでしょうか。
そういった意味で「チベット死者の書」はいろんな見方ができる映像作品だと思います。長い間、人間がずっと守ってきた、儀礼や知恵が詰まっている。必ず生まれ変わるという輪廻転生を信じるのも、人間の一つの知恵ですよね。そうした内容だからこそ、放送から15年も経った今、DVDにしていただいて、多くの人に見てもらえるんだなと思います。
現在のチベット、そして日本について
現在のチベットについては、独立に関連した番組などは作っていませんが、その後もいろんな形でもお付き合いは続いています。ただ、現地には行っていません。撮影当時の鮮明な記憶、というか、全てが焼き付いていますから。
今後のことを考えると、ダライ・ラマの存在が益々重要になってくると思います。今回のDVDには、番組取材当時に行ったダライ・ラマのインタビューも収録されています。最近のインタビューだとどうしても政治的なものが多くなってしまいますが、ここでは仏教そのものの話をすごくわかりやすく話してくださっていて、とても説得力があります。本当にチャーミングで、自由で、大変な魅力がある方だと思います。
振り返って日本のことを考えてみると、毎月3000人もの自殺者が出る時代に、宗教の側から何かできないものかという気がします。経済不況になり、いろんな十字架を背負うことになった人達を救う手立てが何もないのかと思います。宗教だけではなく、コミュニティなど、いろいろ可能性はあるはずです。僕自身も「チベット死者の書」で一つ句読点を打って別のことをしてきましたが、DVDが出たことをきっかけにもう一度、立ち戻らなければいけないかなと思っています。
プロデューサー河邑厚徳 「制作の裏側」 その1
それはシルクロードから始まった
今回発売されたDVD「チベット死者の書」の特典リーフレットにも書きましたが、チベットと最初に出会ったのは80年代の始めにNHK特集「シルクロード」の「秘境ラダック」編を作った時でした。実はラダックに入る前に、川を流れている子供の死体をカメラマンと一緒に撮影したことがありました。タージ・マハルという夢のように美しい宮殿の裏を流れるガンジス川の支流、ヤムナ川でした。見ていると川に入った野良犬が死体をくわえて川岸に戻り、食べ出したんですよ。そのうち、犬の周りにニ重三重の輪ができていく。最初の輪は禿鷹などの大きな鳥達。そして、その周りにまた小さな鳥が待っている。わずか30分くらいで、川を流れてきたその死体が白骨化してゆくのを目撃しました。その時、僕はがんで死にゆく患者さんを映像で追いながら日本の末期医療を描いた「ドキュメンタリー・がん宣告」という番組を作った直後でした。日本では死が隠され、病名も告知しない、末期医療のケアもない時代でした。そうした、本当に救いのない状態を見た後インドに行き、病院での死の対極ともいえるむきだしの死を目の前に見て、「死は当たり前の事実だ。人間は死から逆算して生きなきゃ嘘になる」」気づき、「生き抜く」という事が自分のテーマのようなものになりました。
その後、ラダックに行き、密教の教えと共に生きる人々と出会いました。日本人の自分からするとラダックは地理的には遠い秘境ですが、日本の大乗仏教につながるようなところもある。最終的には、信仰が生きている社会で暮らす人々がいかに平和で、欲望のままに物質を求めるような、そういう世界とは違うものがまだ生きているという事を実感し、大感動しました。そして、「いつかこの事を番組としてやらなきゃいけない」という思いが原点になって、それから約10年後の、「チベット死者の書」につながっていきました。
「チベット死者の書」が2部作になった理由
いわゆる“秘境”を撮影する場合、都会に暮らす私たちと比べて、何か特別な世界で風土も違うし文化も違うと、まるで博物館に並んでいる珍しいものを見るような目線で見ることがあります。僕は「チベット死者の書」では、そういうもの珍しさと対極にある作品が作りたいと思いました。ラダックに住んでいる人たちも、同じ人間で、生まれていつか死ぬことは全く共通です。だから、まるで違う宇宙にでも暮らしているように思われているチベットの人達の姿を撮ることで、日本に限らず、文明国と呼ばれる地に暮らしている人達に「命や生を実感しているのか?」「本当に充実した人生を送っているのか?」ということを問いたいと思いました。チベットにはチベット仏教が強く生きていて、人間には肉体や物質だけではなく、心や精神というものがあるという考え方がしっかりと受け継がれている。それを知っているチベットの人達が、驚くほど生き生きと幸福そうに生きているという事実に感動して、そういう点を伝えようと思った。違いではなく、共通性を見ようとしたんですね。
さらにそれを番組にする時には、1本目はオーソドックスなドキュメンタリー、2本目はシナリオがあるドキュメンタリードラマと、あえて2本にしたいと思いました。一つの真実があった場合、表現の仕方にはいろいろあって、別にどっちが嘘だとか、どっちが真実だという事ではない。視聴者に伝えようとしている事をよりはっきりと伝えられるのはどちらだろうか、というチャレンジをしてみようという気持です。映像にはいろんな方法論があるし、自由に作っていいはずだ。そういう事をあえて、やってみようと思いました。
NHKスペシャル「チベット死者の書」は1993年の秋に放送されましたが、実は92年から93年にかけて、日本の映像メディアにとって、大きな出来事がありました。92年の秋に放送されたNHKスペシャル「奥ヒマラヤ禁断の王国・ムスタン」という番組に対して、「NHKがムスタンでやらせの番組を作った」という記事が93年2月の朝日新聞に掲載されたのです。これに対して「やらせだ」と強く批判する人と、「映像でものを作る際には、前もっていろんな準備があるし、再現も含めたいろんな自由な手法がとられるべきだ」と主張をする人が真っ向からぶつかり、半年くらいにわたって、いろんな形で紙面をにぎわしました。
ちょうど僕らは92年の1月にチベットに入って取材を進めていたので不思議な縁を感じましたね。ムスタンもやっぱり標高3800メートルくらいのヒマラヤの古いチベット文化圏でしたから。途中で合流したディレクターが持ってきてくれた新聞を読んだり、その後の一連の出来事を見たりしながら「日本ではドキュメンタリーに対して、非常にナイーブで単純な見方しかないんだな」という事を痛感しました。ドキュメンタリーというのはカメラの前で起っている事を、ただ撮って編集すればいいというものじゃない。作品を作るためには、いろんな準備も、演出も必要です。ただ、「奥ヒマラヤ禁断の王国・ムスタン」についていえば、手法上、誇張したり、あまりうまくない再現を使ったりしたところもあると思います。でもそれは技法の問題で、「嘘をついた」と、倫理的に、あたかも犯罪者のように糾弾する話ではないと思います。
そういう意味では、同じような場所で撮影した素材を、ドキュメンタリーとシナリオがあるドキュメンタリードラマという2本の作品として仕上げ、「映像で何かを伝えるということは、こんなにも幅があるものなんだ」という事を訴えたいという気持がありました。もちろん、それは僕の裏の意図みたいなところですから、この番組を見てそこまで深読みした人は誰もいないかもしれません。ただ、「あの番組はどうして2部作になったのか」という背景には、映像メディアの歴史にとって大きな事件があったという事を思い出して見てもらえると、映像を考えるヒントにもなるのではないでしょうか。
プロデューサー 河邑厚徳
放送から15年後に、このようなDVD企画が実現した不思議に感謝しながら、あらためて埋蔵経(テルマ)の不思議を感じています。現代が必要とする死の教えがそこにあるからです。
河邑厚徳(かわむら・あつのり)
1948年生まれ。NHKエデュケイショナル統括エグゼクティブ・プロデューサー。ドキュメンタリー「仏典に秘めた輪廻転生」、ドキュメンタリードラマ「死と再生の49日」の企画・制作を担当。
歓びにみち笑いながら死んでいけばいい 山川健一
ずっと観たいと渇望していた映像を、遂に観ることができた。それがこの「NHKスペシャル チベット死者の書」である。内容は、ドキュメンタリーとストーリィとふたつになっている。中沢新一氏が制作に携わったというだけあり、どちらも期待を遥かに上回るものだった。
ご存知のように、『チベット死者の書』は西欧社会に紹介され、アンダーグラウンドカルチャーの全盛期だった1960年代末から70年代にかけて世界的なベストセラーになった。世界とは何か。自分とは何か。そんな根源的な問いに多くの若い人たちが向かい合った時代だった。ぼくもそんな中の一人だった。
だが短い学生生活はすぐに終わり、ぼくは23歳で作家デビューすることになった。
わけも分からず、小説を書きつづけた。文学というものにこの身のすべてを投じるのだ、と本気で思っていた。
時代も、上昇気流にのっていた。
拡大へ。拡散へ。
まったく新しい未知の価値を探して、胸いっぱいに新鮮な空気を呼吸する毎日であった。やがてレゲエとパンクロックがシーンを席巻し、経済はふくらみつづけ、科学のシーンではまったく新しいコスモロジーを紡がれつづけた。DNA、進化論、量子力学、コンピュータ、インターネット。そんなものを追いかけつづける過程で、ぼくは大切なものを失っていることに気がついた。大切なもの。それは、世界とは何か、自分とは何かという根源的な問いである。
ゼロ・ポイント・フィールドやホログラフィック・ユニバースというhttp://ameblo.jp/yamaken/最新の科学的な概念に出会った時、ぼくはそのことにハッと気がついた。
「あれ、これって空海が言ってたことやチベット密教が言ってたことと同じだ!」
振り出しに戻るというやつである。
だったら自分の30年とは何だったのか?
科学の歴史は、ぼくらの知覚がいかにあやふやなものにすぎないのかを明らかにしてきた。ぼくらは地面は平らで動かないものだと知覚しているが、実際には地球は球体で、しかもものすごい速度で自ら回転しながらさらに太陽の周りを周回している。
ぼくらの肉体を含めて物質は原子で構成されているが、原子核と電子の間は巨大な空っぽの空間で、だがどうやらその空っぽだと思われていた空間は振動しているらしい。
手で触れれば硬い鉱物だって、そのコアは空っぽなのであり、しかも振動しているのだ。人間の知覚的な経験をベースにした物質主義は、こうして見ると、社会的な制約そのものに他ならないのではないだろうか。社会的な制約の中で、ぼくらは五感によって得た情報だけで現実を構成している。五感だけに頼っている限り、その社会的な制約の外の世界を知ることはできないのだ。
そういうことが、どうやら遥か昔、空海やチベット密教においては自明の理だったらしい。ふと気がつくと『チベット死者の書』の新訳や、新しい関連書籍が何冊か出版されており、ぼくは空海関連の書籍といっしょにそれらを片っ端から読んだ。ひどく古い時代の知恵なのに、不思議と最新の英知が辿り着いたコスモロジーと一致する世界観が、そこにはあった。
そしてぼくは、1993年に「NHKスペシャル チベット死者の書」が制作されていたという事実を知るのである。しまった、と思ったがもう遅い。あちこち探しまわったのだが、この番組のビデオを入手することはできなかった。かわりに、河邑厚徳氏と林由香里氏が執筆しNHK出版から出た番組と同名の書籍は購入することができた。
ある日、ジブリの方から連絡をいただき、その探し求めていた映像がDVDでリリースされることを知ったのである。そういうわけで、ぼくはこの原稿を書いている。
圧倒的な映像である。
そいつは美しいが、ビーチと海が美しいとか、そういうレベルではない。
ドキュメンタリー 「仏典に秘めた輪廻転生」においてカメラは「バルド・トドゥル」を読み聞かされる死者の顔をアップでとらえる。死に臨む人の耳元で49日間にわたって読み聞かせる「バルド・トドゥル」は、いわば死後の旅のガイドブックなのである。
ドキュメンタリードラマ「死と再生の49日」では、アニメーションが効果的に使用され、死後の旅そのものを追体験させてくれる。「バルド・トドゥル」の内容について老僧と少年僧とが対話し、それを聞いている視聴者がごく自然にその内容を理解できるようになっている。
人間は何のために生きているのか。
この人生には意味があるのだろうか。
そんな問いに、ドラマの最後に老僧がヒントを与えてくれる。
ぼくらが泣きながら生まれてくる時、周囲の人々は歓びの声をあげる。ぼくらが死んでいく時、周囲の人々は泣き、だが死んでいくぼくら自身は歓びにみち笑いながら死んでいけばいいのである、と。
山川健一(やまかわ・けんいち)
1953年、千葉県生まれ。作家・ロックミュージシャン・アメーバブックス取締役編集長。早稲田大学在学中より執筆活動を開始。『天使が浮かんでいた』で早稲田キャンパス文芸賞を受賞。1977年、『鏡の中のガラスの船』(講談社)で群像新人賞優秀作受賞。代表作に『さよならの挨拶を』(中央公論社)『水晶の夜』(新潮社)『ロックス』(集英社)『安息の地』(幻冬舎)など。最近作は『幸福論』(ダイヤモンド社)『イージー・ゴーイング頑張りたくないあなたへ』(アメーバ・ブックス)など。最新刊は『リアルファンタジア 2012年以降の世界』(アメーバブックス新社)。
ブログ『イージー・ゴーイング » http://ameblo.jp/yamaken/
「チベット死者の書」とは 石濱裕美子
精神の探究者であるチベット人がつみあげてきた智慧の書
肉体が機能を停止し最後の息がでたあとの49日間、死者は意識だけの状態(パルド)となり、その後新しい母胎に入って再生する、このような輪廻思想がチベットにはある。そして『チベット死者の書』には、このパルドの期間、死者がパニックを起こさず切り抜けられるように、導くための教えが記されている。
肉体を失った意識はもろもろの外界の刺激から離れることによって穏やかになり、もっとも根源的なものに触れることができる。チベット人にとって死は「仏の意識」(菩提)にもっとも近づくことのできるまれなチャンスであるため、死について積極的に話題にするし、命の期限を宣告されても動じることなく受け入れる。高僧に至っては、死に臨んでは、座禅をくんで瞑想に入り、その中で「死の光明」を迎える。深い瞑想と死は限りなく同じ状態であると考えられている。
『死者の書』によると、肉体が死んだ直後、死者はもっとも微妙な意識の現れである根源的な光と出会う。もし死者の意識がその光の中に入っていくならば仏の境地を得ることができる。しかし、これまでに積み重ねてきた様々な行為の力により、死者の意識はすぐに光の状態から引き戻されてしまう。しばらくすると、死者の意識にはやさしい姿の仏たちが現れる。そして、次の一週間にはその仏たちが今度は恐ろしい忿怒の姿をとって現れ、様々なヴィジョンや音で死者を脅かす。そして最後の一週間、死者の意識はついに母胎を探す再生の旅に入り、次の生へと移行する。
この書の素晴らしいところは、49日にわたって現れる光やヴィジョンはすべて死者自身の意識が作り出したもので一切が幻想であると何度も強調するところである。つまり、『死者の書』とは、精神の探求者であるチベット人がつみあげてきた意識のありようについての智慧の書なのだ。したがって、ここに説かれている光とは、宗教や人種をとわず死に瀕した人が見るという臨死の光や音にも通じる。
現実を別の側面から見直そうとするたびに、思い出されてきた書物
チベットには死者の書が数多くあるが、カルマリンパが発掘したこの『死者の書』が一番注目を浴びているのは、この書がこれまでに何度も世界的な大ブームをひき起こしてきたからである。はじまりはイギリスの神智学者エヴァンス・ベンツがオックス・フォード大学から1928年に出版したこの書の初英訳が、たちまちベストセラーとなり、カール・ユングをはじめとする当代の知識人の愛読書となった。六十年代に入ると、ハーバート大学のティモシー・リアリー博士がLSD体験と『死者の書』に描かれる死者の体験が類似していることを指摘したため、『死者の書』はLSDを吸い反戦を謳うヒッピーたちのバイブルとなった。また、七十年代以後は、生の世界ばかりに目を向け、死の世界を等閑に附してきた現代文明への反省として「メメントモリ」(死を思え)が叫ばれ、『死者の書』は臨死体験の書物として脚光をあびた。
日本においては、1993年にNHKスペシャルでこの『チベット死者の書』が放映されるや臨死体験の一大ブームが始まり、この番組の第一部を書籍化した『チベット死者の書 仏典に秘められた死と再生』(NHK出版)と、第二部の台本を収録した中沢新一氏の『三万年の死の教え』(角川書店)と、チベット語原典からの死者の書の和訳である『原典訳チベット 死者の書』(ちくま学芸文庫)がいずれもベストセラーにランクインし、みながこぞって死について語り始めた。つまり、『チベット死者の書』は我々が今ここにある現実を別の側面から見直そうとするたびに、思い出されてきた書物なのである。
不安にみちた現代人にこそ
チベット人の社会は物質的にはきわめて貧しいレベルにあるが、彼らの心は我々よりずっと平穏である。普段から死を生の一部として意識し、来世に備えて体や言葉や心で善い行いを積むように心がけているため、死を前にしても動じることはない。彼らにとって死は、古くなった着物を脱いで新しい服を着るような感覚であり、怖れるべきものではない。
一方、我々の世界は物質的には豊かであるものの、その心はじつに不安定だ。経済成長が人々に幸せをもたらすという幻想のもと、物欲を肥大させ、競争心や嫉妬心をあおった結果、多くの人は心に不安を抱えるようになった。死の間際まで死をまったく無視して生きるため、死に直面せねばならなくなった時、ひたすら恐怖して一分一秒でも長く生きようとする。生まれてから死ぬまで不安にみちたこの現代人の心を鑑みるとき、今こそ、生のもう一つの半分、死に対する知識を取り戻すべき時がきていることは明かであろう。『死者の書』はその一助となるはずである。
日本で『死者の書』がブームになった1993年の4月、わたしは母をガンで亡くした。たった一人の家族を失った喪失感から、眠れない日々を過ごしていたが、この書を手にし、その根源的な死生観に触れた時、ずいぶんと心が落ち着いたことを記憶している。生は死の一部であり、忌むべきものではないことに気づき、自分の人生を見直す契機ともなった。
親しい方を亡くした方、また近い将来亡くすかも知れない方には、とくにおすすめしたい。
石濱裕美子(いしはま・ゆみこ)
1962年、東京都生まれ。早稲田大学教育・総合科学学術院教授。文学博士。研究対象はチベット仏教世界(チベット・モンゴル・満州)の歴史と文化。著書に『図説チベット歴史紀行』(河出書房新社)『チベット仏教世界の歴史的研究』(東方書店)『チベットを知る50章』(明石書店)など。訳書に『ダライ・ラマ仏教入門』(春秋社)、『ダライ・ラマの密教入門』(光文社)がある。
人類学者 中沢新一
こんなとてつもない内容をもった教えの体系が、ごく日常的な手さばきで取り扱われている文化があるということ自体が、現代では驚異的としか言いようがないのではないだろうか。
中沢新一(なかざわ・しんいち)
ドキュメンタリー 仏典に秘めた輪廻転生/協力
ドキュメンタリードラマ 死と再生の49日/脚本







